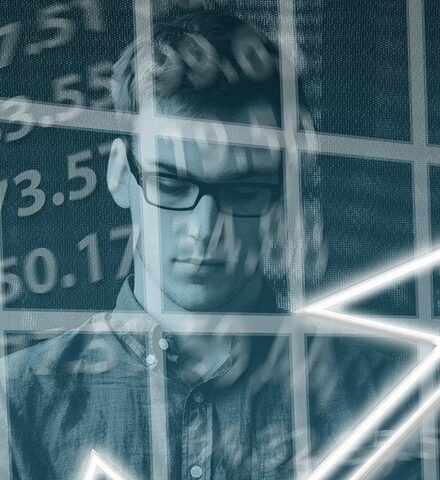|
海洋生物の必須元素としてのケイ素と鉄 ビーエルテック株式会社相談役 元兵庫県水産技術センター所長 眞鍋武彦 地球を構成する元素で最も多いのが鉄で約35%、続いて酸素約30%、3番目に多いのが硅素約15%であり、マグネシウムを加えた4大構成元素で地球の90%以上を占めることが知られている。地表近くの構成元素を表したクラーク数によると、最も多いのが酸素49.5%、硅素25.8%、アルミニウム7.6%、鉄4.7%と続く。このように地球にとって非常に重要な元素である鉄・硅素と生物の関係を見てみる。
~ 海の歴史~ 46億年前の地球の誕生以来、地球の冷却と共に約40億年前に海洋が生まれ、その後約35億年前に最初の生命が誕生した。約27億年前には藍藻類が登場し、藍藻類の誕生は大陸と海洋の形成に大きい役割を果たした。藍藻類は二酸化炭素を吸収し酸素を放出したため、還元状態にあった海洋は大きく変化を遂げて行くことになった。溶解していた大量の鉄は酸化され不溶化し海底に堆積した。現在採掘されている縞状鉄鉱床である。ほとんどの鉄が沈殿堆積したあと、剰余の酸素は大気中に放出され大気圏酸素濃度が上昇し始め、生物の陸上進出を可能にした。約19億年前に火山活動が活発になり大きい大陸が形成された。ゴンドワナ大陸に先立つ最初の大陸ヌーナ大陸である。このころ真核生物が出現した。このように生物の関与の中で海水中の溶存成分濃度は変化し、約2億年前に至り主要成分組成は定常状態 になり、以降一定に保たれている。
~ 海水の組成~ なるほど海の主要11成分組成は一定に保たれており、川から流入する元素の海での平均滞留時間から見ても、最も短い炭酸水素イオンで8万年、最も長い臭素イオンで1億年と算出され、深層水の混合が1000年単位であることから成分組成は非常に安定であると言える。他の微量成分も多くは1万年以上の滞留時間を持っているが、ここで取り上げる鉄は100年程度と短い。また平均滞留時間1000年以上でも濃度の均一性を保証するものではない。燐、硅素、窒素などは海域での生物利用が活発であるため不均一な分布となる。このように窒素、燐、硅素、鉄は海洋生物に吸収されるため表層域では濃度は低くなり、生物が沈降分解する間保留するため深層域で高濃度を示すこととなる。海洋生物内での滞留時間は物理化学作用による滞留時間に較べると遙かに短い。窒素と燐は非保存性の栄養塩として広く認識され、栄養化問題や生物一次生産の重要指標となっているが、硅素と鉄に関して重要性の認識は低く、断片的な研究成果が散見されるに過ぎない。
~ 硅素と鉄~ ここでは人間活動による海洋環境劣化の“つけ”として、今後の研究が期待されている硅素と鉄に目を注ぐ。先述したように硅素と鉄は海洋で生物の関与によって不均一成分としての挙動を示す。沿岸域では硅素も鉄も陸上そして海底層から大量に供給されるため、生物活動に関与するほど欠乏することはなく、生物生育の制限物質となることは先ずない。ただ流入河川の少ない内海域沖などで発生した珪藻類の赤潮時に硅素が枯渇しているとの報告はある。鉄に関しても直接的な調査結果資料は見ないが鉄不足により生物生産が低い海域があること、生物生産力を増強するため鉄を大量に海に散布する構想など、近年注目を浴びている。また海水への鉄の溶解度は低く、海水中に存在する鉄の多くは錯体鉄として生物活性に関与しているとの重要な成果が報告されている。 珪藻類にとって硅素は細胞の骨格を形成する必須成分で、硅素の枯渇環境で珪藻は増殖し得ない。沿岸域では珪素が枯渇することはほとんどないため硅素が優占することが多 く、硅酸塩濃度が減少し他の栄養塩類が多いときには渦鞭毛藻類、ラフィド藻類が優占し魚介類の成育を阻害することがある。近年、内海域では秋季から春季にかけての大型珪藻類の異常発生が養殖のり生育を阻害し大きい問題となっている。 また硅素は陸上植物にとっても非常に重要な成分で、ことにイネ科植物の骨格形成元素として必須で、イネ藁の10~20%、藁灰の50%を硅酸が占めている。 生物界で鉄は非常に重要であらゆる生物が鉄を必須とする。鉄溶解度の低い畑などで育てた植物は成長が抑制されビタミンA不足で黄変するし、藻類も微量の鉄を必須とし、枯渇した環境では一次生産力が著しく低下する。このように硅素も鉄も生物界では非常に重要で、今後その存在量やその代謝を十分に把握対応する必要がある。また枯渇した場合の対策などについても研究を進める必要がある。筆者は硅素もそして鉄も、陸域からの供給が不足した場合、海底土や陸水に多量に含まれる硅素や鉄錯体を効率よく利用することが非常に重要なことと考えている。その技術開発が望まれる。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
第6回オートアナライザーシンポジウム開催報告
オートアナライザー協会主催の「第6回オートアナライザーシンポジウム」が、2010年6月11日に大阪スカイビル36階にて開催されました。 住友金属テクノロジー株式会社試験部部長岡圭男様の「流れ分析法による水質分析への適用例」をはじめ、オートアナライザーによる海、湖沼の環境調査の発表等がありました。 特に今回のシンポジウムでは、注目されています流れ分析のJIS化の動向についての発表が社団法人日本環境測定分析協会会長橋場常雄様からあり大いに関心を呼びました。 講演要旨集をご希望される方は、弊社担当者までご連絡 ください。尚 数に限りがありますので、お早い目にお問い合わせください。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
株式会社環境総合テクノスの栄養塩測定用海水標準物質が 世界的に利用することが推奨されました。
株式会社環境総合テクノスが製造販売する栄養塩測定用海水標準物質(RMNS)が国際的な海洋観測調査マニュアルで利用することが推奨されました。 ユネスコの政府間海洋学委員会(IOC)、国連専門機関の世界気象機関(WMO)などによる「GO-SHIP(ゴーシップ)船舶による全海洋物理・化学調査プログラム」が8月18日付でマニュアルを発行し、RMNSの利用を推奨しました。その中で、環境総合テクノスのRMNSは「均質性と安定性を備える」と唯一紹介されました。 RMNSの利用の推奨は多くの機関、多くの航海、多くのデータの比較可能性を極めて高めることが認められたことによります。データの提出にあたって はRMNSの測定結果を報告することが規定されました。RMNSは当社製品のオートアナライザーの同時多成分分析に対応しており品質の高いデータを提供することができます。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
社団法人日本環境測定分析協会主催 日環協・環境セミナー全国大会in Nagoyaにおいて弊社連続流れ分析法を紹介いたしました。
平成22年10月22日「オートアナライザー新技術のご紹介 環境測定分析における分析業務省力化へのご提案」という演題で発表させて頂きました。 また、今年は東京都、神奈川県、大阪府、福岡県の各環境測定分析事業者協会様にて講演をさせて頂きました。 特に連続流れ分析のJIS化の流れに伴って、環境測定分析事業者の弊社の装置への関心が高まりつつあるのを感じました。 また機会がありましたら、ご要望により発表をさせて頂きます。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
オートアナライザーワンポイントアドバイス
全窒素全リン分析用オートアナライザーにおける分解ラインの特別洗浄方法について
弊社の全窒素全リン分析用オートアナライザーで使用している分解チューブ(テフロン製)の特別洗浄方法(5N-NaOHとH2O2を1:1で混合)については御存知のことと思います。しかしながら、どの程度の頻度で行って頂いていますでしょうか?ここで、もう一度整理しておきたいと思います。 分解チューブの中には、サンプルと分解液(ペルオキソ)が流れていきますが、同時に油分や無機粒子なども流れてしまいます。手分析法のように上澄みを取り、発色試験をすることができないオートアナライザーでは、チ ューブ内壁に汚れが溜まりやすくなります。これの汚れを取り除くためにも特別洗浄がとても重要な役割を果たします。 一例として、汚れ(粒子分)の強い(見た目が濁っている)サンプルを1日50サンプル以上、かつ週 に2~3日運転を想定します。この場合だと2週間ごとに特別洗浄を行って頂くと効果的です。もしくは、ピーク形状が乱れ始めたときまたは分解チューブ内の気泡文節間隔がバラバラになったときを目安でも結構です。 分解チューブも半永久的に使用できるわけではなく、当然交換も必要です。上記の例で運転を継続すると、1年ごとの交換が理想です(そのと きのピーク形状などで判断できます)。また、同時にTNリサンプル、TPリサンプルなどのフィッティング類も交換すると、さらに効果的です。 分解チューブの交換方法につきましては、弊社技術部までお問い合わせ下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
自動吸光光度法分析装置AQ1(ディスクリートアナライザーAQ1)
ディスクリートアナライザーAQ1は、従来販売させていただいていたAQ2+よりコンパクト設計の吸光光度法の自動分析装置です。 1本のプローブにより、サンプル、試薬、混合液の吸引を行いますのでユーザーは、サンプルと試薬をセットし分析条件を設定すれば分析が自動で行えます。
特 長 1.1台で多項目の分析が可能です。 干渉フィルターが7枚設定されており7項目以上の測定ができます。 測定項目例) 排水関連 硝酸+亜硝酸、亜硝酸、アンモニア、りん酸 ボイラー水関連 塩化物、硫酸、りん酸、マグネシウム、カルシウム、アルカリ度など 農業土壌関連 硝酸、アンモニア、りん酸、カリウム、マグネシウム、カルシウム
2.自動分析ができます。 サンプルと試薬の混合および混合液の測定用フローセルへの導入も自動で行います。自動希釈機能がありますので、スケールオーバーしても自動で再測定します。
3.省スペース化を実現します。 装置の横幅が、480mmと非常に小さく省スペースで測定ができます。
4.1時間に最大80テストの分析ができます。 分析処理速度が最大80テストと迅速に分析ができます。
5.銅カドミ還元コイルを装備しております。 硝酸+亜硝酸で硝酸から亜硝酸に還元を銅カドミ還元コイルにて容易に行えます。還元コイルのコーディングも非常に簡単です。
6.サンプル量、試薬量が大幅に少なくなります。 サンプルカップは、1mlまたは2mlと非常に少量です。それに応じて試薬量を少なくなり排液が大幅に少なくなります。
7.ユーザーにてカスタマイズ可能です。 使われるお客様で、サンプル量、試薬量、反応時間など任意に設定できます。これにより新しく自動化できる項目も増えます。
主な仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
同時分析項目数 処理能力 立ち上げ・終了操作 サンプル自動希釈 検量線作成 |
最大7項目 最大80テスト/時 自動立ち上げ、自動停止 オーバースケール試料の自動希釈再検機能あり 自動希釈により検量線を自動的に作成 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
主な測定対象(例) ボイラー水、工程水、工場排水、河川湖沼水、下水、農業土壌抽出液等 <主な測定項目> |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
近赤外分析計インフラスターInfraStar1400
約30年ほど前に、近赤外分析における農産物、食品測定に必要な波長が1400nmから2400nm間の19波長にあることが米国テクニコン社により見つけられました。言い換えれば、この19波長がそろっていれば、ほとんどの農産物や食品中の目的成分が測れるということです。 同社により、その波長を用いたインフラライザーが販売され、世界のベストセラーとなりました。当時大変高価でしたが、費用対効果を考えたユーザーは導入に踏み切りました。日本国内でも800台ほどのインフラライザーが納入されました。 その堅牢性や便益さから、現在も国内外を問わずインフラライザーが使用されています。 今回ご紹介するのは、そのインフラ ライザーの完全互換機であるユニティ・サイエンティフィック社のInfraStar (インフラスター)1400です。
特 長 1.設定価格は、他のメーカーが追随できない低価格にしました。 2.操作がしやすいトップウインドウでパソコン不要のスタンドア ローン。 3.1400~2400nmを1nmきざみで、わずか0.8秒の高速スキャンをします。 4.インフラライザーの更新のみならずDiky-JohnやPertenの更新用にも最適です。 5.過酷な現場に対応するべく耐振、防湿性能は、他社の装置とは比較になりません。 6.約16Kgの軽量性とコンパクト設計。 7.堅牢性と正確性を実現した回折格子には特許が付与されています。 8.検量線を無償でサービスします(製粉)。 9.他社の粉体用サンプルカップもお使いいただけます。
この他にも、SpectraStarシリーズがあります。サンプルを回転させる場合やより広域な波長領域を使う場合にお勧めします。 ※お問い合わせは、本社(TEL06-6445-2332)もしくは東京本社 (TEL03-5847-0252)までお願いします。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
コントロールサーベイ(精度管理)のご案内
弊社では、オートアナライザー法による国内での分析値の整合性を調査し、皆様に機器の精度管理および分析技術の向上を目指していただく観点から、コントロールサーベイ(CS)を実施しています。CSは外部精度管理の一つであることから、皆様が行う外部精度管理そして内部精度管理の一端としてもご協力できるものと考えております。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
表1 測定項目と参加施設数
参加総施設数: 153 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
今回は、より詳細な分析結果を得るために他機関で行われている技能試験同様に試料の均質性試験および安定性試験を行ない、同一ロットの試料を提供させて頂きました。配布した試料は、大量調製した溶液を均質となるようによく攪拌し、容器に分取したものです。結果から自施設の分析技術を客観的に認識していただき、今後の品質管理や測定精度の向上に努めて頂ければと思います。
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
発行/ビーエルテック株式会社 |
||||||||||||||||||||||||||||