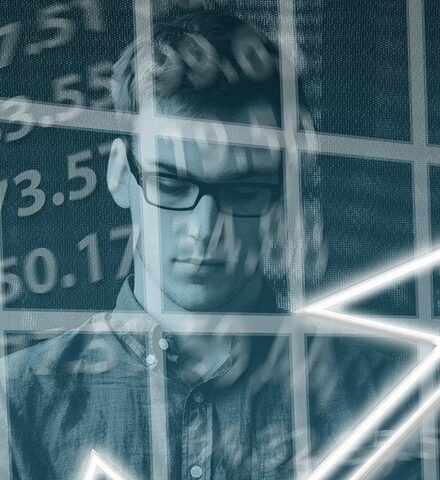|
湖沼の再生に向けて
NPO法人 環境生態工学研究所 理事長 須藤隆一
われわれ国民が快適で健康な生活が送れるよう、河川、湖沼、海域、地下水いずれの水域にも環境基本法に基づいて国が定めた環境基準があてはめられている。水質環境基準は、健康項目と生活環境項目とに分けられている。 健康項目はいずれの水域にも同一の項目と基準値が定められているが、生活環境項目は水域別に異なった項目とそれぞれの水の利用目的に応じた類型が決められている。地下水は健康項目のみで生活環境項目は定められていない。 健康項目は26項目あるが、これを超過する割合はごく わずかで、おおむね基準を達成しているといえる。しかし地下水の亜硝酸性および硝酸性窒素はこの数年5~6%程度超過している地点がみられ、地下水の硝酸性汚染はかなり拡大しているとみなされている。一方、生活環境項目の有機汚濁を示すBOD,CODの達成率は、2003年度で河川87.8%、湖沼55.2%、海域76.2%と最近横ばいの傾向にある。湖沼は測定開始以来はじめて50%を超えたが、低いことには変わりはない。 このため、総務省は湖沼について2004年8月に「湖沼 の水環境保全に関する政策評価」を公表している。その内容は、湖沼水質保全特別措置法(湖沼法)の施行から20年を経過しているにもかかわらず、政策目標である水質環境基準や湖沼水質保全計画の水質目標は大半の湖沼において未達成である、など湖沼の水質に顕著な改善はみられず、総体として期待される効果が発現されているとは認められない、という厳しいものである。このため、湖沼法を所管する環境省から、2004年10月に中央環境審議会に対して湖沼環境保全のあり方について諮問され、2005年1月末に答申が出されている。その骨子は非特定汚染源対策の強化、自然浄化機能の活用および特定汚染源に対する規制の見直しである。非特定汚染源は流出水と位置づけ、対策に必要な地域を指定して、負荷削減を推進する。一方、特定汚染源対策には、下水道への接続の促進、単独浄化槽の窒素・りん除去型浄化槽への転換、小規模排水対策、生活排水全般の窒素・りん除去を強化すること、などがあげられている。これらの答申を受けて湖沼法は改善されることになっている。 湖沼の水環境は、従来からの水質にとらわれることなく、生物、底質、水辺等を含めた環境全体として再生方策を見出すべきである。また水質もCOD、T-N,T-Pのみでなく、透明度、底質のDO、クロロフィルa 濃度等を合せて評価することが望ましい。 しかし、いずれにしても湖沼の環境保全は、陸域からの流入および底泥から回帰するCOD、窒素、りんを削減することより他に方法はない。霞ヶ浦において、第4期の水質保全計画に示された対策が平成17年度までになさ れたとしても、COD8.5%、全窒素1115%、全リン9.4% が削減されるにすぎない。このためシミュレーションに よって予測される水質も現状より濃度が10%程度減少す るのみである。この程度の対策では、第5期、第6期と水質保全計画を策定しても著しい改善は期待できない。貧栄養あるいは中栄養といわれた湖沼でも富栄養化進行の兆しがあり、富栄養化があまり進行しないうちに予防的に保全措置をとる必要がある。その例が猪苗代湖で、条例を制定して指定湖沼と同様な厳しい規制と対策が実施されている。他の湖沼でも少なくとも猪苗代湖と同様なことが実施されることが望まれる。富栄養化が極度に進行してから水質回復を計ることはきわめて難しいことを肝に銘ずるべきである。次に湖沼環境保全のいくつかの課題を示す。 ①流域管理として湖沼をとらえ、土地利用を制限する必要がある。 ②非特定汚染源対策、とくに市街地排水、農業排水についての負荷削減方策に取り組む。 ③生活排水および工場・事業場排水の窒素、りん除去を小規模排水まで含めて実施する。 ④水辺帯(エコトーン)を修復する。 ⑤外来種の移入拡大を防ぎ、種の多様性の維持・向上を確保する。 このような課題と取り組むうえで、窒素・りんの測定 は不可欠である。ビーエルテック社製オートアナライザーが十分に活用されることが期待される。
|
|
|
|
オートアナライザーシンポジウムの開催にあたって
オートアナライザ協会会長 三重大学教授 前田広人
先にご案内のとおり、このたび新たにオートアナライザー協会を発足させて頂きました。発足にあたりましては、関係各位の皆様方のご協力に厚くお礼を申し上げます。 さて、我が国においては、雨水から海水にわたる水質の形成過程において人為的な汚濁負荷が増加し良好な水質を維持することが困難となりつつあります。この水環境を保全するにあたって重要なことは高度のモニタリング技術と水質の改善技術です。 このような状況に鑑み、本協会は、環境モニタリングの高度化に即し、オートアナライザーを通して、水質分析の高度化および水質保全に資するための技術的支援と会員相互の情報交換の場を提供することを目的として発足 いたしました。 そして、本協会の活動の一環として、後にご案内いたしますとおり、毎年一回オートアナライザーシンポジウムを開催いたします。シンポジウムのテーマ設定にあたりましては、会員の皆様からのご意見をいただきながら、話題性および必然性のあるテーマを順次取り上げさせていただければと考えております。また、できるだけ自由闊達な意見交換ができる会議の場であるよう心がけたいと存じます。 第1回目のオートアナライザーシンポジウムというこ ともありまして、大半の方々が初顔合わせになると存じます。そのため、借越ながら私の基調講演「これからの水問題」のなかでご紹介いたします以下の話題提供を もって、口火を切らせていただきます。
これからの水問題 1.閉鎖性水域の富栄養化 湖沼など陸水における赤潮やアオコは依然として頻発 しています。とりわけアオコの発生は近年にも増して各所で頻発するようになってきており、各自治体から相談が寄せられています。また海域では昨年だけでも1O億円以上の赤潮による漁業被害が報告されています。九州ではコックロディニウム、瀬戸内海などではギムノデニウムやヘテロカプサなど現場観測の結果を紹介しながら、現在行われている対応技術などについて紹介いたします。
2.地球温暖化に伴う陸水および海水温上昇 近年の観測結果から、ここ数年鹿児島湾など閉鎖性海域の海底水温は平年より2℃上昇していることが明らかにされています。過去10年間にわたる鹿児島湾の水塊構造の変化を海水温上昇の観点から見直し、栄養塩の鉛直分布 がいかに変化しているかを紹介します。また、いくつかの湖沼では温暖化による、表層水温の上昇に伴って冬季の鉛直循環が不完全となり湖底の無酸素化が懸念されている事例を取り上げたいと存じます。その他海水温上昇と磯焼けに関する情報についても報告いたします。
3.地下水の硝酸塩濃度の上昇 畜産が盛んな九州の各地では、近年畜産排水によると思われる地下水の硝酸塩濃度の上昇が懸念されています。 すでに飲料水としての基準値から大幅に逸脱する地域が出始めています。戦後から続く畜産業の長期的かつ急激な増加による負荷が顕在化しているとの見方がある一方 で、農耕地からの過剰な肥料による負荷であるとの見方もあり、今後注意深くモニターする必要があると思われ ます。
4.水産養殖とゼロエミッション化 開放系で行われる水産養殖は自家汚染という宿命と直面 しながら行われてきました。ある水域では、窒素負荷の3割は水産養殖からの残飯や糞尿であると推測されてい ます。近年、この自家汚染対策の一つとして複合養殖によるゼロエミッション化が試みられています。一例としては、養殖筏の周りに海藻を植え付け、窒素とリンを海藻に吸収させ、収穫した海藻を貝類に与えて餌料として循環させていく方法が挙げられます。
5.食糧生産と水 今更言うまでもありませんが、食糧の生産には水が必要です。我が国で生産せず、輸入に依存している食糧に ついても、視野を拡げ、その背景には莫大な水の消費をともなって生産された物であることを再認識する必要があると考えます。すなわち地球規模で水を洞察し管理することも今後の我々の研究課題となるのではないかと考えております。
以上、これから我々が直面するであろういくつかのテーマを挙げさせていただきます。まだこ案内通り各先生方の講演では更に深く掘り下げたお話を伺えるものと楽しみにしております。 どうか、皆様方のふるってのご参加をお願い申し上げ ます。
|
|
発行/ビーエルテック株式会社 |