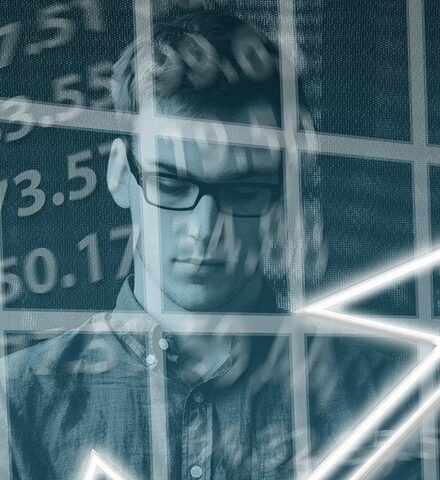|
国内産粗飼料生産の推進と近赤外分光分析法が担う役割 三重県科学技術振興センター畜産研究部 大家畜研究課 博士(学術)主任研究員 平岡啓司
我国の畜産は,食生活の多様化などを背景として発展をとげ,農業総産出額の約28%を占める農業分野での基幹産業となっている。このように畜産物の生産拡大を実現できたのは,輸入飼料に大きく依存するといった世界的にみても類のない加工型畜産に因るものであるが,一方では,我国の食料自給率を低下させる一因ともなっている。さらに,ここ数年,土地への依存度が極めて低くなっている日本型畜産のあり方を問い直す大きな問題が発生している。すなわち,2000年の口蹄疫の発生に続き,翌年のBSEなどの国際感染症の発生や食品の虚偽表示問題,スターリンクの混入問題など,輸入飼料依存との関わりが指摘され、我国の飼料基盤や食の安心・安全に対する消費者の関心がかつてないほどの高まりを見せている。
このような状況に対応して,2001年に制定された「食料・農業・農村基本計画」では,2015年の食料自給率を45%,飼料自給率を35%にすることを目標に掲げ,国内の主要な飼料生産基盤を①従来からの草地・飼料畑を基盤とする自給飼料多給・資源循環型畜産,②水田における飼料イネ,水田裏作を基盤とする水田活用型畜産,③中山間地の里地,里山,遊休地,公共牧場を基盤とする日本型放牧畜産に類型化し、それぞれの技術開発を行っていく必要性を提示している。とりわけ,食用イネ栽培技術の準用も含めた耕畜連携強化による地域農業の活性化や、家畜堆肥の土地還元による循環型農業の推進など、多様な畜産的土地利用の一貫としての飼料イネ生産利用技術の開発に期待が寄せられている。
従来より、近赤外分光分析法は、迅速かつ低コストな分析法として実用化され、穀類をはじめ乾草やサイレージ等の栄養成分を迅速に把握する上で今や必要不可欠な存在となっている。当研究部では、「飼料イネ」という新たな粗飼料の生産推進を図るため、飼料イネの栽培、調製、給与に至る一貫した技術体系の開発に取り組み一定の成果を得ることができた。とりわけ、水田に家畜堆肥を還元する際の成分調査や飼料イネの栄養成分の評価に関する分野においては、近赤外分光分析法を用いた迅速分析法を提案し生産現場からも評価を得ている。 先述のとおり、輸入飼料に依存した我が国の畜産業は、原油・飼料価格の高騰や地球温暖化に伴う異常気象等の影響を受け極めて厳しい状況にある。
今後、土地に立脚した「土-草-家畜」といった資源循環型畜産を科学的根拠に基づき推進するためには、近赤外分光分析法の担う役割はさらに大きくなると考られる。 |
|
|
(当部使用のNIR 近赤外分析装置) |
|
|
インフラライザー500 (ブラン・ルーベ社)
|
スペクトラスター2400 (ビーエルテック社) |
|
|
|
|
Trans Starを用いた検量線用データの移設 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 畜産草地研究所 畜産研究支援センター 中小家畜飼養技術研究室 甘利雅拡
私、現勤務先で近赤外分析装置を利用した研究をしております。主に、家畜飼料の栄養成分・栄養価・堆肥成分・家畜生体液成分などの分析に使用しており、これらのサンプルデータも膨大になってきています。
当研究室ではメーカーが異なる近赤外分析装置を2台を導入しています。1台は、BRAN+LUEBBE社製InfraAlyzer500、もう1台は、NIRSystems社製Model6500です。それぞれ、導入後かなりの年数が経過しており、後継を検討する時期に入ってきています。最近、新たな機器が多く開発され、また、製造が既に終わっている機種もあり、後継機種へのデータの移設について考慮しておく必要を感じております。
この度、データベースを移設できるソフトウエア があると聞き、ビーエルテック社にデモンストレーションをお願いいたしました。今回、デモをおこなったサンプルは、牧乾草、牧草サイレージで、ベースの機器はNIRS6500です。
まず、手順をご説明いたします。
1:NIRS6500とSpectraStar2400(UnityScientific社製・ビーエルテック社販売)を並行して稼働させます。 2:同一サンプル(2~30サンプル)をそれぞれの装置で測定します。今回は実際のサンプルを測定しました。<移設計算の為のデータ収集> 3:NIRS6500で採ったデータフォーマットを(検量線用、計算用共に)SpectraStar2400のフォァーマットに変換します。<trimstar使用> 4:それぞれのデータを、検量線計算ソフトに読み込みます。 5:TransStarを起動し、手順に従い計算を実行します。 6:CalStarを用い、検量線の計算をおこないます。
今回の一連の操作で、所要時間(解析を除く)は2時間以内で完了しました(手順3~5の所要時間は、10分程度で終了しました)。これは、検量線作成及びバリデーションサンプルのスペクトル測定し、解析し直すのと比べて、かなりの労力が軽減できます。これまでの方法ですと、データの取り直しをすれば少なくとも数日間の時間を作業に取られますし、過去のデータで、現在サンプルを準備できないものもあり、再現が難しいこともあります。一方、「データをそのまま移設できます」という、メーカーの言葉があっても、実際にその可能性を検証する方法も無い状況の中で、TransStarはこの様な検証をした上での移設ということもあり、高い信頼が持てます。実際、移設したデータで検量線を作成し、既知サンプルで検証したところ、移設前の精度と同等のデータが得られました。このソフトウエアは、特に我々の様な研究機関においてで、過去に収集した多くのデータを有効利用したいユーザーに対し、強力にサポートできるものと考えます。私たちも今後、大いに活用したいと考えております。
しかし、現在ではサポートしている装置は、SpactraStarへのデータベースの移設のみで、使う側にとっては、その他の装置へも、もう少し柔軟に対応できないものかとも思います。いずれにしましても、今後の検討材料としていただき、より一層の発展を望ものであります。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
オートアナライザーワンポイントアドバイス 試薬の保存期間 試薬の保存期間は、食料品の賞味期限と同様にその製造方法、保存方法、環境によって異なります。用事調製と指定した試薬以外の試薬の化学的安定性は意外と長いものが多いのですが、保存方法、環境(カビとかが多い施設)により結構異なる場合があると考えられます。
1) 要冷の必要がない試薬は室温保存ですが、その温度は約20℃位であり、夏場ではその期間は半分以下になります。 2) 冷所保存とは約4℃位の冷蔵庫保存を意味します。 3) 試薬に界面活性剤(50% TritonX-100, 15%SLS)を添加した試薬はカビなどにより急激に劣化することがありますので、1週間以上のものは要注意です。 4) 添加用の界面活性剤(50% TritonX-100, 15%SLS)は、調製後一ヶ月で作り直した方が安全です。特に15%SLSはできるだけ20℃位の恒温槽に保存してください。
以上のほかに、調製に用いる器具、容器、純水は十分に注意して汚れのコンタミネーションがないようにすることが前提条件です。
|
|
|
|
|
|
地球温暖化の一因である炭酸ガス濃度とオートアナライザー 2007年のノーベル平和賞は、国連の「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)(Intergovernmental Panel on Climate Change、IPCC)と、米前副大統領ゴア氏に贈られた。 授賞の理由は「地球温暖化は人間の行為によって起きていることを明らかにし、それに関する広範な知識の蓄積と普及に努め、必要な対応策の基礎づくりに貢献したこと」である。このなかで、大気中の炭酸ガス濃度の増加が地球温暖化の一因であると言われている。 18世紀後半から人類の産業活動が活発になるにつれ、化石燃料消費の急増による温室効果ガスが大量に大気中に放出され、その結果、大気中の温室効果ガスの濃度が高まり、熱の吸収量が増えて気温が上昇する。これが、炭酸ガスによる地球温暖化と言われている。 気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の報告によれば、過去約100年間で全地球の平均地上気温が0.3~0.6℃上昇し、温室効果ガスがこのまま増え続けると2100年には、さらに1.4℃~5.8℃上昇すると予想されている。地球規模で気温が上昇すると、海水の膨張や氷河などの融解により海面が上昇し、気候メカニズムの変化により異常気象が頻発する恐れがあり、結果として自然生態系や生活環境、農業などへの影響が懸念されている。 陸上で発生した炭酸ガスの一部は森林等により吸収、消費されているが、また、一部は海洋が炭酸ガスを吸収していると言われている。大気中には炭素換算で7000億トン滞留しているのに対して、海洋に大気中の炭酸ガスが溶け込んで出来る炭酸は現在34兆5000億トンとも言われている。また人類が産業活動にともなう化石燃料の消費等により年間70億トンの炭酸ガス(炭素換算)が排出され、その内半分が大気中に残り、炭酸ガス濃度を増加させ、残りの大部分は海洋に吸収されていると考えられている。 このように海洋は地球温暖化の一因である炭酸ガスと深く関わっている。 オートアナライザーは、現在多くの海洋関係で栄養塩等の測定に用いられている分析装置であるが、実はその他に多くの項目の測定が可能である。例えば海水中の炭酸ガス吸収メカニズムに関係する指標として注目されている、アルカリ度、全炭素、炭酸ガス濃度等の測定も可能である。 オートアナライザーの多量の検体を少ない時間で処理できる測定スピード、省力化を活かして、次の地球環境や海洋生物の生態系保護活動にも弊社の技術を活用いただければ幸いである。 オートアナライザーによるこれら測定に関心をもたれた方は、是非弊社までお問い合わせを頂きたい。 |
|
|
|
|
|
QuAAtroHR-2 新機能!! ソフトウェアーオートダイリューション TRAACSによる栄養塩等の測定で、従来ピンチバルブを使用してオートダイリューションを実行させていた方法はQuAAtro HR-2とその新ソフトウェアーにより、一回の測定(RUN)で実行完了する機能に進歩しました。 QuAAtro HR-2は24bitでデータ解析を行っており、設定測定範囲を超えてスケールオーバ(チャート上振り切った)した高濃度のサンプルピーク高もDigitalメモリーできます。 そのソフトオートダイリューションはDual Rangeとよばれ以下のように測定されます。 1) 通常の測定範囲(例:0-1mg/l)で測定され、もしスケールオーバーした高濃度サンプルがあれば、その直後のサンプル(2個)を、測定後自動的に再検します。 2) その後、高濃度の測定範囲(例:0-10mg/l)用の標準液を吸引して、高濃度用の設定に自動変更されます。 3) 高濃度用の設定で、先の測定でスケールオーバーした高濃度未知サンプルの濃度を計算します。 通常測定範囲、高濃度測定範囲とも、それぞれ検量線、ピークチャートを見ることができます。 この機能により、従来のオートダイリューションに要した時間はなくなりました。 |
|
|
発行/ビーエルテック株式会社 |
|