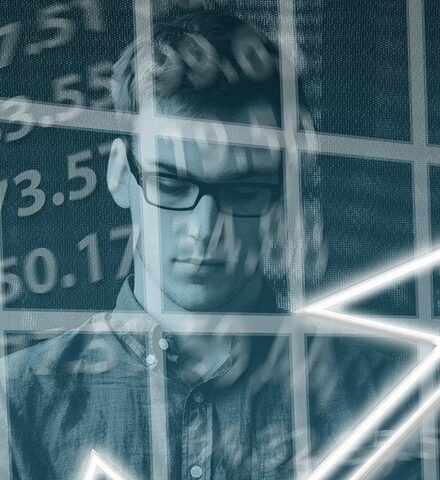|
第4回オートアナライザーシンポジウムのご案内
第4回オートアナライザーシンポジウムを2008年6月13日(金曜日) 大阪梅田スカイビルにて開催いたします。
■日時 平成20年6月13日 午後1時より5時40分まで予定 ■場所 梅田スカイビル タワーウエスト 36階 『スペース36』
|
|||||||||||||||||
| 13:00-13:10 | 挨拶 オートアナライザー協会 会長 前田広人 | ||||||||||||||||
| 13:10-14:20 | 基調講演「環境問題と国際政治」 中部大学 総合工学研究所(副所長) 教授 武田邦彦 |
||||||||||||||||
| 14:20-14:55 | 「フィールド研究におけるオートアナライザーの応用例」 京都大学 フィールド科学教育研究センター 森林生物圏部門 森林生態保全学分野 和歌山研究林長 准教授 徳地直子 |
||||||||||||||||
| 14:55-15:30 | 「地下水中の硝酸イオン等のオートアナライザーでの分析 - 事例」 金沢大学大学院 自然科学研究科 物質工学専攻 環境・生物システム講座 准教授 川西琢也 |
||||||||||||||||
| 15:30-16:00 | 休憩 | ||||||||||||||||
| 16:00-16:35 | 「これからの計量証明事業所の進むべき方向」(国際規格1S0/lEC17025認定試験」所について) 日本認定試験所協議会(ATLC)副会長/環境総合研究機構株式会社 代表取締役社長 日本総研株式会社 代表取締役社長 大石一成 |
||||||||||||||||
| 16:35-17:10 | 「常願寺川右岸扇状地における浅層地下水中の硝酸性窒素の動態」 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 中央農業総合研究センター 北陸研究センター 田畑輪換研究チーム 主任研究員 大野智史 |
||||||||||||||||
| 17:10-17:40 | 「第2回コント□一ルサーベイ(精度管理)のご報告」 ビーエルテック株式会社 技術部 西村崇 |
||||||||||||||||
| 18:00-20:00 | 交流会 (会場1周フロア ご参加料11,000円) *ご参加料は、当日会場受付にてお支払いください。 *事前登録制です。 |
||||||||||||||||
|
ごあいさつ |
|||||||||||||||||
お陰様をもちまして、今年も第4回オートアナライザーシンポジウムを開催する運びとなりました。このシンポジウムは分析装置であるオートアナライザーを通じて、顧客の学術的交流をしていただく場をご提供するものであります。 事務局として、このような社会的に意義のある活動に貢献できることを誇りに感じております。 またシンポジウム終了後、演者の先生方との交流会もご用意させていただいておりますので、ご多忙中大変恐縮ではございますが、交流会にも是非ご出席くださいますようご案内いたします。 |
|||||||||||||||||
|
オートアナライザーシンポジウム開催事務局 ビーエルテック株式会社 代表取締役 川本和信 |
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
近赤外分光分析法による大豆の機能性成分含量の推定
独立行政法人 農研機構・九州沖縄農業研究センター 佐藤哲生・西場洋一
九州沖縄農業研究センターは、熊本にあります。九州地域にある農業研究センターとして、私たちは、(暖地)農産物の品質評価・機能性評価の研究を担当しています。そのなかの最近の研究成果を紹介することにしましょう。大豆は、優れた伝統的な食品をつくる素材ですが、新規食品をつくる素材としても利用されています。その需要拡大を図るためには、より高付加価値の大豆を作出することが重要です。これらに役立てようと、私たちは、これまでに、大豆の製油工程管理のための指標や大豆の脂肪酸組成などを測定するために、近赤外分光分析法(近赤外法)による簡易迅速測定法の研究を行ってきました (1,2)。 近年、大豆の消費二一ズは、急速に高度化・多様化し、主要成分のほかに、特徴的な栄養成分・機能性成分にも注目が集まっています。こうした状況の下に、SpectraStar2400(写真、Unity Scientific、米)と統計解析ソフト:SensoLogic (Sensologic GmbH、独)を用いて、大豆粉末あるいは丸のままの大豆複数粒計測で、大豆の機能性成分:イソフラボン・ビタミンB類(チアミン、リボフラビン)・トコフェロール(ビタミンE)類の含量推定法の検討を行いました(3)。 材料として、日本各地で栽培された大豆を用いました。大豆粉は、超遠心粉砕器(Retsch、独;節目=1mm)で調製しました。イソフラボン、ビタミンB類、トコフェロール類は、高速液体クロマトグラフィーで測定しました(4)。標準カップに粉砕した大豆粉を充填して、あるいは、全粒セルに丸のままの大豆を複数粒充填して、近赤外スペクトルを測定しました(測定装置: SpectraStar2400、波長:1200~2400nm、1nm step、測定方式:拡散反射モード)。得られた近赤外スペクトル値および化学分析値を用いて、キャリブレーション用、ブレディクション用に試料群を分け、一解析ソフトウェアSensoLogicで、重回帰分析、PLSR/PCRの統計解析を行いました。 重回帰分析の結果、大豆粉の測定では、イソフラボン総量は、近赤外法による推定が可能でした。図は、そのプレディクションの結果を示しています。イソフラボンは、配糖体、マロニル配糖体、アセチル配糖体、アグリコンで構成されていますが、そのなかでも含量の多い配糖体、マロニル配糖体の個別の推定も可能でした。また、総トコフェロール含量の推定可能性も示唆されました。ビタミンB含量は、変動幅自体が小さかったので、推定精度が低下しました。一方、全粒測定では、粉体で測定する場合よりも、精度が低下しましたが、イソフラボン総量は、近赤外法による非破壊推定が可能でした。さらに、PLSR/PCR解析でも、重回帰分析と同様の傾向が得られました。 近赤外法は、大豆の主要成分分析の公定法として、すでに利用されています(5)。これまでの知見(1,2)や、今回の知見(3)により、近赤外法が、より幅広く用いられ、大豆分析法としての地位を固めていくことを望むものです。
<引用文献> 1)Sato T, et al,: J. American Oil Chemists’ Soc., 71 (10):1049-1055(1994). 2)Sato T, et al.; J. American Oil Chemists’ Soc., 79 (6):535-537(2002). 3)佐藤哲生ら:第23回近赤外フォーラム講演要旨集,p116(2007). 4)西場洋一ら:日本食品科学工学会誌、54(6)295-303(2007〉 5)USDA FIGS:Near-Infrared Transmittance(NIRT)Handbook(1996).
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
近赤外分析計インフラライザーのアフターサービスについてのご案内
ビーエルテック株式会社は、2006年にドイツブラン・ル一べ社の分析事業部を譲渡買収した英国SEAL社と独占業務提携をいたしております。 また英国SEAL社はドイツブラン・ルーべ社の近赤外分析計インフラライザーのアフターサービスを正式に契約し引継ぎを行っております。 従いまして、日本国内において、弊社は近赤外分析計インフラライザーの唯一正式なアフターサービス・部品供給会社としてサービス業務を継続して行っております。 しかしながら、近赤外分析計インフラライザーシリーズの古いタイプにはアフターサービス用の一部部品には、入手に時間(3ヶ月~6ヶ月)を要する場合がありますことをご理解賜りますようお願いいたします。 尚、旧インフラライザーシリーズの後継機種として、弊社では近赤外分析計スペクトラスターシリーズを市場にリリ一スしております。当該機器は旧インフラライザーの互換機として開発され、現在ご使用中の検量線の移設も可能な機種となっております。
ビーエルテック株式会社
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
水道局・下水道局向けオートアナライザー 全窒素全リン測定専用オートアナライザー
STAT-2000TNTP 水道局・下水道局向けに新たにオートアナライザーSTAT-2000型TNTPをリリースしました。 この装置は従来の全窒素全リン分析用オートアナライザーSWAAT型を専用機化した装置で、全窒素全リン測定専用の装置です。 連続オートクレーブにて分解後、全窒素はJIS K 0102紫外吸光光度法、全リンはモリブデン青(アスコルビン酸還元)吸光光度法によって測定します 比較的有機物の多い下水道局等のサンプルにはサンプラーに超音波ホモジナイサーをオプションで取り付けることも可能です。
特長 *1時間に約20サンプルを測定可能。 *40本掛けのオートサンプラーを標準装備。 *サンプル、試薬、廃液が非常に少量。 *分析途中で検量線を作成し、結果を表示。 *サンプラーと本体の設置スペースは、横幅約150cmと非常にコンパクト。 *気泡分節型連続流れ方式(CFA)を原理とした高精度、高感度分析。 *サンプラーにオプションで超音波ホモジナイサーを装着可能です。
硝酸窒素測定用オートアナライザー
STAT2000型NOx
硝酸性窒素汚染は、生活排水や農業排水の多い河川水の浸透が原因であるとされています。硝酸性窒素は体内に摂取すると、亜硝酸性窒素に還元され酸素を運ぶ赤血球のヘモグロビンと結合し、乳幼児の酸素欠乏症を誘引し、また発がん性物質であるニトロソアミン類の生成に関与するといわれている。 我が国では環境基本法に基づき定められている「水質汚濁に係る環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準」が1999年2月に改正され、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が環境基準項目に追加されている。2001年7月には水質汚濁防止法施行令が改正され、硝酸化合物等が有害物質に追加指定され、排水規制、地下浸透規制等の対象となりました。 硝酸(追加項目:亜硝酸、アンモニア)測定 JIS K0102-43.2.3 銅・カドミウムカラム還元-ナフチルエチレンジア ミン吸光光度法に準拠した分析法を採用しています。
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
オートアナライザーワンポイントアドバイス
オートアナライザーの硝酸測定は、JlS K0102-43.2.3銅・カドミウムカラム還元-ナフチルエチレンジアミン吸光光度法に準拠した分析法が用いられています。 分析に用いられるカドミウムカラム、カドミウムコイルは、銅イオンによる適切な前処理(マニュアルを参照)を行うことで硝酸の亜硝酸への高い還元率を得ることができます。 一般の環境水(海水・河川水等)に於いて硝酸濃度は亜硝酸の20~30倍程度を含有していると考えられます。 具体的に、硝酸:20ppmと亜硝酸:1ppmのサンプルをモデルといたしますと、還元率100%の場合:サンプル硝酸(20ppm)+亜硝酸(1ppm)は21ppmとして観測されます。次に還元率90%の場合:標準液も同一条件で処理されますので硝酸は20ppmとして観測されますが、亜硝酸部分は[1×100/90=1.111]1.111ppmとして観測されますので、硝酸+亜硝酸は21.111ppmとして高く観測されます。 結論と致しまして、20倍の濃度差が有れば測定誤差 (21.111/21.0=1.0053)は0.53%となります。30倍の濃度差が有れば0.36%の誤差となります。10倍の濃度差の場合でも1.01%の誤差に収まります。 以上、還元率の管理は多くの環境水に於いて、90%を一つの管理指標としてご検討されることをご提案いたします。
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
第2回 コントロールサーベイ
弊社では、皆様からのお声もあり、国内での分析値の整合性、今後の機器の精度管理、分析技術の向上への参考資料になることから、一昨年前からコントロールサーベイを実施しています。内容は、こちらから4種類の試料を発送させていただき、一定期問内にご使用されているオートアナライザー等で測定した項目および値を、各施設毎にご報告頂くといった形式のものです。昨年、12月下旬に行った第2回コントロールサーベイでは、131施設からのご参加があり、一昨年前に行われた第1回コントロ 一ルサーベイに比べ61施設増の参加をして預けたことを誠に喜ばしく思います。各測定項目に於ける参加数は、以下の表の通りでした。
ご参加頂いた測定項目と施設数
参加総施設数:131
ご参加頂きました施設には、ご報告頂いた測定値の平均値、標準偏差、および全施設平均値を示した結果デー タ表、平均値からの変動を示したTwinPlot図、直線性図をお送りさせて頂きました。
弊社におきましても、お客様へのサービスの向上、機器の精度管理、維持管理技術の向上に繋がる資料になると確信しております。 お忙しい中、ご参加いただき誠にありがとうございました。今後とも多くの施設のご参加を期待しております。よろしくお願いします。
|
|||||||||||||||||
|
発行/ビーエルテック株式会社 |
|||||||||||||||||